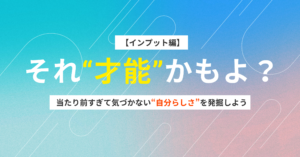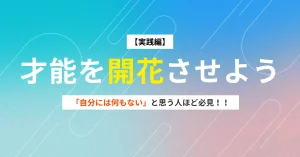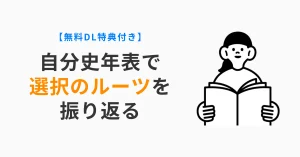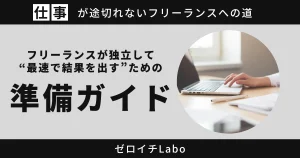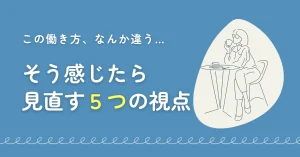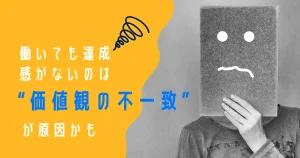好きなことを仕事にしたいは逃げ?なぜあなたが好きなことを仕事にできないのか、その背景を徹底解説します。
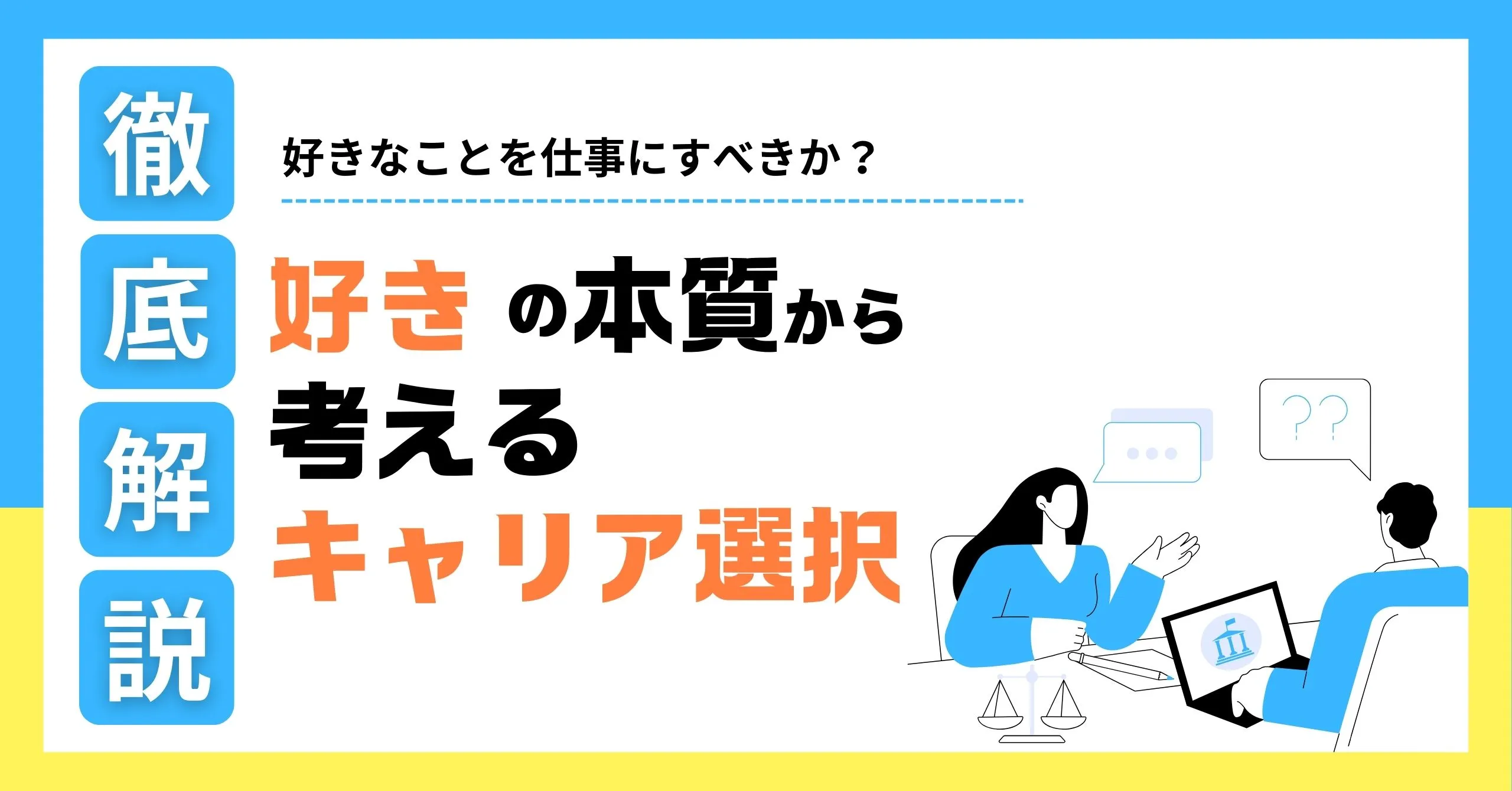
導入
「好きなことを仕事にする」と聞くと、多くの人が「好きなことだけしていられる」「毎日が楽しい」といったポジティブなイメージを抱きがちです。
しかし実際には、好きなことを仕事として成立させるには、努力はもちろん、嫌な作業や苦手分野も切り離せません。
「自分には音楽が好き」という自覚があっても、演奏が好きなのか、曲を作るのが好きなのか、あるいは誰かの演奏を聴くのが好きなのかによって、必要なスキルや取り組み方、成果の出し方は大きく変わってきます。
本記事では、「好きなこと」の本質をとらえたうえで、好きなことを仕事にすべきかどうかを見極めるための視点やステップをまとめました。
単なる感情論ではなく、冷静な自己理解と現実的な判断をするためのヒントとして参考にしてみてください。
1. 「好きなこと」とは何なのか 〜“好き”を言語化する力〜
1-1. 「好き」を表面的に捉えていないか?
私たちは「好きなことは何ですか?」と聞かれると、ついジャンルや対象そのものを答えがちです。
たとえば、次のような回答が多く聞かれます。
- 音楽が好き
- 映画が好き
- 旅行が好き
- ファッションが好き
- ゲームが好き
けれども、それだけでは職業選択やキャリア形成には活かしにくいと言えます。
なぜなら、「何が好きか」ではなく「どう好きか」「何に惹かれているか」こそが、自分らしい仕事につながるヒントになるからです。
つまり、“好き”という感情をもっと細かく、深く、具体的に掘り下げる必要があるのです。
1-2. 「何をしているときが好きだったのか?」という視点
例えばですが、「音楽が好き」と言っても、そこに含まれる行為や役割は非常に多様です。たとえば…
| 対象 | 好きな“行為”の例 |
|---|---|
| 音楽 | ・演奏するのが好き ・作曲するのが好き ・機材をいじるのが好き ・音を分析するのが好き ・ライブの空気感が好き ・誰かの演奏を応援するのが好き |
| 旅行 | ・計画を立てるのが好き ・写真を撮るのが好き ・現地で人と話すのが好き ・日常から抜け出す感覚が好き |
| ファッション | ・服をコーディネートするのが好き ・自分を表現するのが好き ・トレンドを分析するのが好き ・人に似合う服を選ぶのが好き |
このように、“好き”の中には必ず「自分が何をしているときに心が動いていたか」という体験があるのです。
仕事にするという観点では、この「行為」に注目することがとても重要です。
なぜなら、職業とは“行為の連続”だからです。
何を対象にするか以上に、自分が「どんな動き方」「どんな役割」「どんな過程」を楽しんでいるかを知ることで、仕事とつながるヒントが得られます。
1-3. 「好き」は感情ではなく、“エネルギーの向かう方向”
「好き」という感情は、突き詰めれば自分のエネルギーが自然と向かう方向性を指しています。
たとえば、
- 気がつくとその情報を調べている
- 無意識にその話題に反応してしまう
- 疲れていてもついやってしまう
- 他人に説明したくなる、語りたくなる
このような状態のとき、私たちは理屈抜きでその対象や行動に惹かれています。
つまり、「好き」とはただの感情ではなく、“自分のエネルギーが流れる先”を教えてくれる羅針盤でもあるのです。
この感覚に気づくには、「過去に何を夢中でやっていたか」「どんなときに時間を忘れていたか」など、子ども時代や学生時代、趣味の時間などを丁寧に振り返ることが役立ちます。
1-4. 「快」と「意味」が重なると“本当の好き”が見えてくる
“好き”には2つの要素があります。
- 快感としての「好き」
→ 楽しい・気持ちいい・ワクワクするのような、いわゆる「達成感」と言われるもの- 意味としての「好き」
→ 意味がある・価値がある・誰かの役に立っている実感
この2つが重なったとき、「好きなことを仕事にする」という感覚は強くなります。
たとえば、
- 絵を描くのが楽しい(快)+ 誰かが喜んでくれる(意味)
- 話すのが好き(快)+ 人を勇気づける力になっている(意味)
- 情報を調べるのが好き(快)+ 人の意思決定に役立っている(意味)
このように、「快」と「意味」が重なる場所を見つけることで、単なる趣味ではなく仕事としての“好き”が具体化していきます。
1-5. “好き”を言語化する3つの問い
最後に、“好き”をより深く理解するための自問自答フレームを紹介します。
- どんなときに時間を忘れるほど没頭していたか?
→ 夢中になった瞬間には、あなたの本質的な欲求が表れています。 - お金をもらえなくてもやっていたことは何か?
→ 純粋な興味や関心が現れている可能性が高いです。 - 他人から「なんでそんなことができるの?」と言われたことは何か?
→ あなたにとって当たり前でも、他人にとっては特別な強みであることがあります。
まとめ:好きなことの“芯”を探せ
「好きなことを仕事にする」というのは、実は非常に“抽象度の高い問い”です。
だからこそ、安易にジャンル名や趣味を並べて終わらせず、「何をしているときに心が動いたのか」「どんな意味を感じていたのか」という“行為の本質”を掘り下げる必要があります。
表面的な「好き」ではなく、「自分のエネルギーが自然と向かう方向」「やっていて快+意味を感じること」を見極めること。
これが、後々“好きなことを仕事にする”という選択を本当に自分ごととして成立させるための、最初で最も大切なステップです。
2. 好きなことを仕事にするための前提条件 〜「夢見がち」から「現実的な実現力」へ〜
2-1. 嫌なこと・できないことを知っているか?
「好きなことを仕事にしたい」と考える人が陥りがちなのが、「好きなこと=苦しさがない」「好きなこと=毎日楽しい」という誤解です。
しかし、現実の仕事では必ず以下のような“面倒くささ”がセットでついてきます。
- 細かい事務作業
- 顧客対応、クレーム処理
- 集客や営業活動
- 確定申告、経費管理
- プロモーション、SNS運用などの発信活動
どんなに好きなことであっても、こういった「やりたくないこと」「苦手なこと」にどう向き合うかは避けて通れません。
むしろ、「好きなことを継続するために、どこまで我慢できるか? どこから人に任せるか?」を考える必要があります。
✔ 自分の「やらなくて済む方法」を考える
- 自分がやると消耗する作業 → 自動化 or 外注
- 嫌なことが得意な人をチームに入れる
- 苦手な工程を避けられるビジネスモデルに切り替える
「好きなことを続けたいなら、嫌なこととの付き合い方を設計する」。
これが、夢を現実に近づける第一歩です。
2-2. 少ない努力で成果が出やすい領域を把握しているか?
「好きなことを仕事にしたい」と考えたとき、その“好き”が仕事として通用するかどうかの判断材料のひとつが「成果が出やすいかどうか」です。
✔ ここで注目すべきは、「得意なこと」と「人よりラクにできてしまうこと」
自分では「当たり前」と思ってやっていたことが、他人から見れば「すごい」「なんでそんなことできるの?」と驚かれる。
この感覚は、仕事における圧倒的な武器になります。
【例】
- デザインが「感覚的に」できてしまう
- 複雑な情報を「わかりやすく整理」するのが得意
- 人の話を「自然に深掘りしてしまう」コミュニケーションスキルがある
こうした“自分にとっては自然にできること”は、好きと重なると大きな可能性を秘めています。
なぜなら、「ストレスが少ない状態で成果が出せる」からです。
✔ 自分に問いかけてみてほしいこと
- 他の人が苦労しているのに、自分は簡単にできることは何か?
- 無意識にやってしまっていることで、周囲に感謝されたことは?
- 他人に教えると驚かれたスキルはあるか?
2-3. 判断基準を持てるほどの経験値があるか?
好きなことをいきなり仕事にしようとしてもうまくいかないケースが多いのは、「判断材料が足りない」からです。
✔ 「やってみないとわからない」ことがほとんど
- そもそも自分に本当に向いているのか?
- 続けたときにどのくらいの苦労があるのか?
- お金になる可能性はどれくらいあるのか?
- お客さんに喜ばれるのはどんな要素か?
こういった問いに答えられるようになるには、“現場での試行錯誤”が必須です。
✔ まずは「小さく試す」
- 副業として、知人にサービスを提供してみる
- SNSで発信して反応を見る
- 無料でもいいから、実際にやってみて人の感想を聞く
机の上で考え込むよりも、「やってみた→反応があった→改善する」のサイクルを回すほうが、遥かに早く確信を得られます。
2-4. ビジネスモデルへの視点があるか?
どれだけ好きで得意であっても、「お金を生まない構造」では仕事になりません。
✔ 自分の「好き」を仕事にするためには、その周辺に“ニーズ”があるかを考える必要があります
- 誰の、どんな問題を解決できるか?
- 自分の好きなことで、どんな価値を提供できるか?
- それに対して、誰かが“お金を払ってでも欲しい”と思うか?
たとえば…
| 好きなこと | 価値提供 | 仕事への展開 |
|---|---|---|
| 旅行好き | 珍しい場所や体験のシェア | ブログ運営、旅行プランナー、インフルエンサー |
| イラストが好き | 作品に想いを込める | LINEスタンプ、グッズ制作、挿絵受注 |
| 人と話すのが好き | 聞き手として安心を与える | コーチング、カウンセリング、営業職 |
✔ 好きなこと=商品ではない。価値提供の形を再定義する
「好きなこと」をそのまま売ろうとするのではなく、「それを通じてどんな価値を渡せるか」という視点が重要です。
仕事にするとは、「価値交換の場に立つこと」です。
まとめ:好きだけじゃダメ。でも、好きは強い
- 好きなことを仕事にするには、「嫌なこととの付き合い方」を考えることから始まる
- 成果が出やすい領域=自分の才能や強みが隠れている可能性がある
- 判断基準は、経験からしか育たない。考えるより、まず小さく試す
- 「好きなことそのもの」よりも、「好きなことを通じて届けられる価値」がカギ
夢だけで突っ走ると挫折する。
でも、戦略的に“好き”を活かす方法を選べば、現実的に仕事にしていくことは可能です。
「好きだからやる」ではなく、「好きなことを活かすにはどう設計すればいいか?」と考える。
その視点こそが、“好きなことを仕事にする”ための現実的なスタート地点になります。
3. 「好きなこと」を仕事にするための心構え 〜「自分軸×現実軸」で人生をデザインする〜
「好きなことを仕事にしたい」と思ったとき、多くの人はスキルや方法論を先に探しがちです。
しかし、どんなスキルを身につけるにせよ、どんな方法をとるにせよ、その土台となるのは「心構え=マインドセット」です。
ここができていないと、続かない・折れる・ブレるという壁に何度もぶつかります。
この章では、好きなことを「継続的な仕事」に変えるために必要な3つの心構えについて、具体的に見ていきましょう。
3-1. 自己理解を深める:「好き」+「得意」+「価値」を見つける
仕事にするということは、自分が持っているものを“他者に提供する”ということです。
そのためには、まず「自分とはどんな人間なのか?」という理解が必要不可欠。
✔ 3つの視点で自己理解を深めよう
- 好きなこと(情熱・ワクワク)
→ どんなことをしていると時間を忘れるか?
→ お金が発生しなくてもやってしまうことは? - 得意なこと(才能・優位性)
→ 他の人よりも簡単にできてしまうことは?
→ 人から褒められること、頼まれることは? - 価値を感じること(意味・意義)
→ なぜ自分はそれをやるのか?
→ どんな未来に貢献したいと思うのか?
この3つが重なる領域が、「自分が自然体で働けて、かつ社会に価値を提供できる」フィールドになります。
✔ 自己理解のためのヒント
- 幼少期・学生時代に夢中になっていたことを思い出す
- 嫌いなこと・苦手なことを言語化する
- ジョハリの窓(自分の認識と他人から見た自分のズレ)を活用してみる
3-2. 自己効力感を育てる:「できるかも」を信じられる力
✔ 自己効力感とは?
「自分はこの状況でも、なんとか乗り越えられる」「うまくやれるかもしれない」という自己への信頼感。
この“自信の芽”がないと、たとえ好きなことでも一歩踏み出せなかったり、失敗のたびに「やっぱり無理だ」とあきらめてしまいがちです。
✔ 自己効力感を育てる3つの方法
- 小さな成功体験を積み重ねる
→ 最初から完璧を目指さず、1つのアクションに区切る。
→ たとえば「知人にサービスを提供してみる」「SNSに発信して反応をもらう」など、“やってみた→反応があった”という感覚が何よりの燃料になります。 - 他人の成功事例を“参考に”する
→ 「あの人でもできたなら、自分もやれるかも」と思えるモデルを見つける。
→ ただし、比較して落ち込むのではなく、“自分のやり方”を見つけるための材料にする。 - フィードバックを得る
→ 客観的な意見や感想をもらうことで、自分の価値に気づける。
→ 他人に褒められて初めて「自分にはできることがある」と思えるケースは多いです。
3-3. 自己受容を身につける:「今の自分」でまずはOKと思えるか
「好きなことを仕事にしたい」と思っても、最初から何もかもうまくいくことはありません。
むしろ多くの人が、以下のような“理想と現実のギャップ”にぶつかります。
- 「あの人はすごいのに、自分は全然できていない…」
- 「こんな状態で発信したら、笑われるんじゃないか?」
- 「もっとちゃんと準備してからじゃないと始めちゃダメだ」
こうした“完璧じゃない自分”に対して厳しくなりすぎると、せっかくの「やってみたい」という気持ちすら、自分自身で潰してしまうことになります。
✔ 自己受容とは、「ありのままの自分を認める力」
自己受容とは、今の自分を肯定的に受け止めること。
「自分はダメだ」と思うのではなく、「まだ未熟だけど、それでもやっていい」と思える心の土台です。
ポイントは、“完璧じゃない自分”を認めつつ、それでも進んでいい理由を自分の中で見つけること。
【よくある自己否定の例と、自己受容による転換】
| 自己否定の思考 | 自己受容の視点 |
|---|---|
| 自分には実績がないから発信できない | 実績がないからこそ、リアルな成長記録が価値になる |
| スキルが足りないからまだ仕事にできない | スキルを身につけていく過程こそがコンテンツになる |
| 他人と比べて自分は劣っている | 他人と比べず、昨日の自分と比べれば一歩進んでいる |
✔ 自己受容がなぜ重要なのか?
好きなことを仕事にするには、必ず「継続」が必要です。
そのためには、失敗や停滞のたびに自分を責めるのではなく、「それでも大丈夫。ここからまた進めばいい」と思える柔軟さが必要です。
人は、自己否定しながら挑戦することはできません。
むしろ、「今の自分も悪くない」という安心感があるからこそ、自然体で一歩を踏み出せるのです。
✔ 自己受容を育てる3つのアクション
① 自分を責める言葉を手放す
「どうせ私なんか…」
「またうまくいかなかった…やっぱ無理だ」
こういった言葉は、無意識に自分を否定し、心のエネルギーを奪っていきます。
代わりにこう言い換えてる用にしてみてください。
- 「今はまだ途中なだけ」
- 「できなかった部分が見えたなら、次に活かせる」
- 「ダメだったんじゃなくて、方法が合ってなかっただけ」
言葉を変えるだけで、自己との向き合い方は驚くほど変わります。
② 小さな「できたこと」に目を向ける習慣をつける
自己受容のベースは、「できたこと」に気づく力です。
完璧じゃなくてもいい。「昨日より少し進んだ」「勇気を出して投稿できた」そんな小さな前進を見逃さないこと。
おすすめなのは、「今日のよかったことを3つ書く」習慣。
- 早起きできた
- SNS投稿に1いいねもらえた
- 苦手な人に返信できた
小さな成功体験を日々可視化することで、「私は前に進んでいる」という自信を積み上げていけます。
③ 自分の“弱さ”に許可を出す
「うまくいかないのが恥ずかしい」
「人に頼るのがカッコ悪い」
「ミスしたら終わり」
こういう“完璧主義”は、好きなことを続けるうえで大きなブレーキになります。
でも、現実にはうまくいかないのが普通。
むしろ、うまくいかないことを前提に“工夫する”ことこそ、仕事の本質です。
だからこそ、最初から“弱い自分”を許容し、「人に頼ってもいい」「失敗しても学べばいい」と思えるマインドが、長くやっていく力になります。
✔ 自己受容は、「覚悟」を支える土台になる
最後に大事なことを一つ。
“好きなことを仕事にする”というのは、正解のない道を進むことでもあります。
うまくいかない日も、誰にも評価されない日もあるでしょう。
そんなときに「それでも、この道を選んでよかった」と思えるかどうか。
その支えになるのが、他でもない「自分への信頼」と「今の自分を許せる感覚」です。
自己受容ができていない人ほど、「結果が出ない=自分のせいだ」「まだダメだ」と感じ、途中で諦めてしまいます。
一方で、自己受容ができている人は、「まだ途中。ここからまた積み上げよう」と冷静に向き合い、継続できます。
まとめ:「“好き”を仕事に変える」のは、マインド次第で結果が変わる
- 自己理解が浅いままでは、進むべき方向もブレる
→ 自分の“好き”と“得意”と“価値観”を整理することが土台になる。 - 自信がないままでは踏み出せない
→ 小さな成功体験を通じて「自分でもできるかも」を感じられると、行動力が変わる。 - 完璧を目指すと動けなくなる
→ 今の自分でOKと思える“自己受容”が、継続の力になる。
「好きなことを仕事にする」とは、夢を叶えることではなく、自分という素材を、丁寧に理解し、育て、現実に適用していくプロセスです。
そのプロセスを支えるのが、「心構え」であり「自己との対話」なのです。
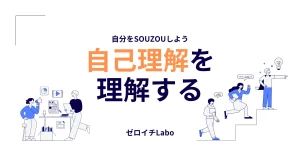
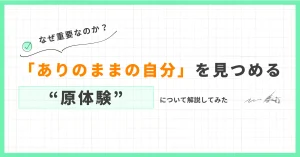
4. 覚悟を固めるまでのステップ
〜“好きなこと”で生きると決める、その瞬間までの道のり〜
「好きなことを仕事にする」と決めるには、ある種の“覚悟”が必要です。
ここで言う覚悟とは、「死ぬ気でやる」みたいな根性論ではありません。
むしろ、「自分はこの道でいく」と他の選択肢を切り捨てて、“不安があっても進む”ことを受け入れる冷静な決断です。
では、どうすればその覚悟が固まるのか?
そのために必要な4つのステップを順に解説していきます。
4-1. 現実を知る:「好き」だけでは成立しないことを理解する
まずはじめに必要なのは、理想と現実のギャップを冷静に見つめる視点です。
「好きなことを仕事にしたい」と思う一方で、以下のような現実が待ち構えています。
- 収益化までに時間がかかる
- 生活費が不安定になる可能性がある
- 周囲から理解されないこともある
- 思ったほど反応が得られないこともある
- 好きなことに「責任」や「義務感」が伴うようになる
これらを“分かったうえで選ぶ”ことが、覚悟の第一歩です。
✔ 知っておきたい現実チェック項目
- 月いくら稼げば生活できる?(固定費+変動費)
- 今の自分のスキルや実績で、稼げる可能性はある?
- 家族や周囲の理解は得られそう?
- 数ヶ月、収入ゼロでも耐えられる備えはある?
これらを整理することで、「やってみたい」ではなく「やるかやらないか」の判断軸に切り替えることができます。
4-2. 小さく試す:「ゼロイチ体験」で確信を得る
覚悟を決めるには、「いけるかもしれない」という根拠のある感覚(=確信)が必要です。
この確信は、頭の中で考え続けても手に入りません。
小さくてもリアルな成功体験があるかどうかがカギです。
✔ ゼロイチ体験とは?
- 初めて「自分の好きなこと」でお金をもらった
- SNSで自分の発信に「共感」の反応が返ってきた
- 誰かの役に立てたという手応えがあった
- 実際にやってみたら、すごく楽しかった・やりがいを感じた
このような「ゼロ → イチ」の体験があると、「あ、自分でもできるかも」という“自己効力感”が一気に高まります。
✔ やってみる具体的アクション
- スキルをココナラ・note・Instagramなどで公開してみる
- 知人やフォロワーに向けて無料 or 低価格で提供してみる
- ブログやYouTubeで発信して、リアクションを観察する
机上の空論ではなく、現場感覚をもつことで「続けられるか?」「向いているか?」「価値があるか?」の判断がつきます。
4-3. 支えてくれる人を持つ:「孤独」との戦いを減らす
好きなことを仕事にすると決めると、時に孤独になります。
特に「普通のルート」から外れるような選択をする人ほど、周囲からの理解が得られにくく、不安が大きくなるのは当然です。
だからこそ、誰か一人でも「いいじゃん、それ」って言ってくれる人の存在が、思っている以上に大きな支えになります。
✔ 周囲の理解・応援があると変わること
- 心理的安全が増し、チャレンジしやすくなる
- うまくいかないときに相談・シェアできる
- 「自分は一人じゃない」と思える安心感が継続を支える
✔ どうやって味方を見つけるか?
- 自分の想いやビジョンを発信する(自然と共鳴する人が集まる)
- 小さなコミュニティに参加してみる(同じテーマの集まりなど)
- コーチ・メンター・ロールモデルを持つ(思考の補強・支援)
人の支えは、覚悟の“後押し”になる栄養剤です。
4-4. 「やりきる」と決める:不安ごと抱えて一歩踏み出す
ここまでのプロセスを経たとき、ようやく出てくるのが「やるか、やらないか」の二択。
覚悟とは、不安がなくなることではなく、“不安を持ったまま進むことを選ぶ”決意です。
どんなに準備をしても、完全に不安がゼロになることはありません。
でも、「それでもこの道を選ぶ」と思えたとき、内側から覚悟が決まる瞬間があります。
✔ 覚悟とは、選択と放棄のセット
- 「この道を選ぶ」=「他の道を選ばない」と決めること
- 「安定」を一部手放してでも、「納得できる生き方」を取りに行く決意
- 「いつかやる」から「今やる」に切り替える一線
そして最後にもうひとつ。
✔ 覚悟は「繰り返し更新するもの」
「覚悟した!」と思っても、1ヶ月後にはまた揺らぐこともあります。
それでもOKです。人間は迷う生き物だから。
大事なのは、一度の覚悟で終わらせず、「なぜこれをやるのか?」を何度も思い出すことです。
覚悟は、一度の決断で終わらず、“繰り返し強化していく信念”でもあります。
まとめ:「覚悟」は静かに、でも確かに心の中で育っていく
- 覚悟は、現実を見てなお、それでもやりたいと思えたときに芽生える
- ゼロイチ体験が、「この道でいけるかも」という自信をくれる
- 仲間・応援者の存在が、不安に立ち向かう力になる
- 不安があっても進むと決めたとき、人は本当に変わり始める
“好きなことを仕事にする”とは、想いや理想だけでは成り立たない。
だけど、理想を捨てたくない人にとっては、現実と折り合いをつけながらも「選び取る」価値のある生き方です。
覚悟を固めるとは、「自分の人生を、自分の責任で生きる」と決めること。
その決意こそが、好きなことを“仕事”に昇華させる最後のピースです。
5. まとめ
〜「好きなことを仕事にしたい人」へ、今のあなたに伝えたいこと〜
「好きなことを仕事にすべきか?」
この問いは、多くの人が一度は向き合うテーマでありながら、答えは人それぞれ異なります。
なぜなら、それは“働き方”の問題であると同時に、“生き方”そのものに関わる選択だからです。
本記事では、以下のようなステップを通じて、好きなことを仕事にするために必要な視点を丁寧に解き明かしてきました。
Step1:好きの本質を言語化する(What)
- 「○○が好き」ではなく「何をしているときが好きだったのか?」に注目する
- 好き=対象ではなく、“自分のエネルギーが自然と向かう方向”
- 「快(楽しい)」と「意味(価値)」が重なる“好き”が、仕事に結びつきやすい
→ 自分の好きは“何をしているとき”に発動していたのか?思い出してみよう。
Step2:現実的な前提を理解する(Reality)
- 嫌なこと・できないことを把握するのも重要な自己理解
- 成果が出やすい=人よりもスムーズに結果が出せる領域を探す
- 判断基準は、実践を通じてしか育たない
- 好きなこと≠商品。好きなことを通じて提供できる“価値”が仕事になる
→ 好きなことを活かすには、どんな工夫・設計が必要だろう?
Step3:自分と向き合う心構えをつくる(Mindset)
- 自己理解:「好き」「得意」「意味」が重なる場所を探す
- 自己効力感:「できるかもしれない」という感覚が行動を生む
- 自己受容:完璧じゃない“今の自分”でスタートしてもOKと認める
→ 自分の中の“できること・まだできないこと”をフラットに見てみよう。
Step4:覚悟を固めて踏み出す(Decision)
- 現実の厳しさを知ったうえで「それでもやるか」を選べるか?
- 小さなゼロイチ体験が、確信を育てる
- 応援者・支えとなる人がいることで、不安の中でも進みやすくなる
- 覚悟とは、“不安を抱えたまま進む”ことを受け入れること
→ どんな小さなことからでもいい。まずは試してみよう。
好きなことを仕事にする人は、ほんの一握り。でも不可能ではない。
「好きなことだけして生きていける」
これは確かに理想的です。
しかし現実には、「好きなことに“現実を結びつけた人”」だけが、それを成立させています。
大切なのは、夢を見ることではなく、夢に構造と戦略を持たせること。
- 「好きなことは何か?」
- 「どうやったら続けられるのか?」
- 「どんな価値を届けられるのか?」
- 「どうすれば仕事として成り立つのか?」
これらの問いに、時間をかけてでも、自分なりの答えを持とうとする人こそが、“好きなことを仕事にする”スタートラインに立てる人です。
最後に:やるか、やらないかは、あなたが決めていい
「好きなことを仕事にすべきか?」
この問いの答えに、正解はありません。
すべきか、すべきでないかではなく、やりたいか、やりたくないか。
進みたいか、進みたくないか。
それを選ぶ覚悟があるか、まだ準備が足りないか。
すべて、自分で決めていいのです。
あなたが「好きなことを仕事にしたい」と心から思うなら、そのための準備を始めてみてください。
完璧な自分じゃなくていい。まだ途中の自分でいい。
“今のあなた”が動き出すことが、すべての始まりです。
あわせて読みたい