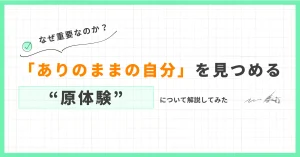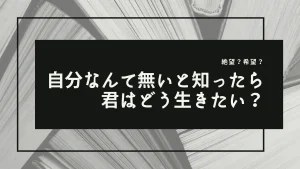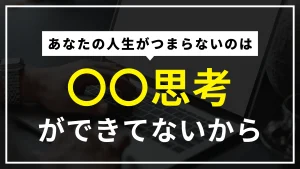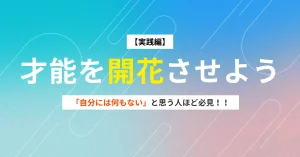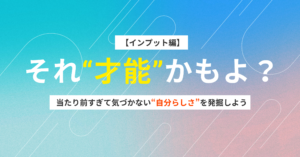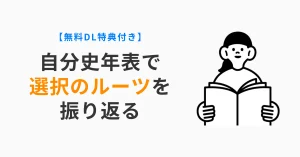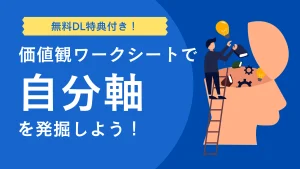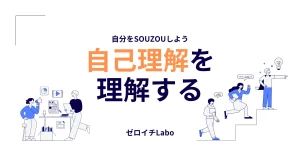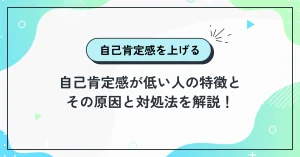やりたいことが見つからない人は全員〇〇思考!?自分の心に嘘をついて死ぬ時に後悔したくない人だけ読んでください。
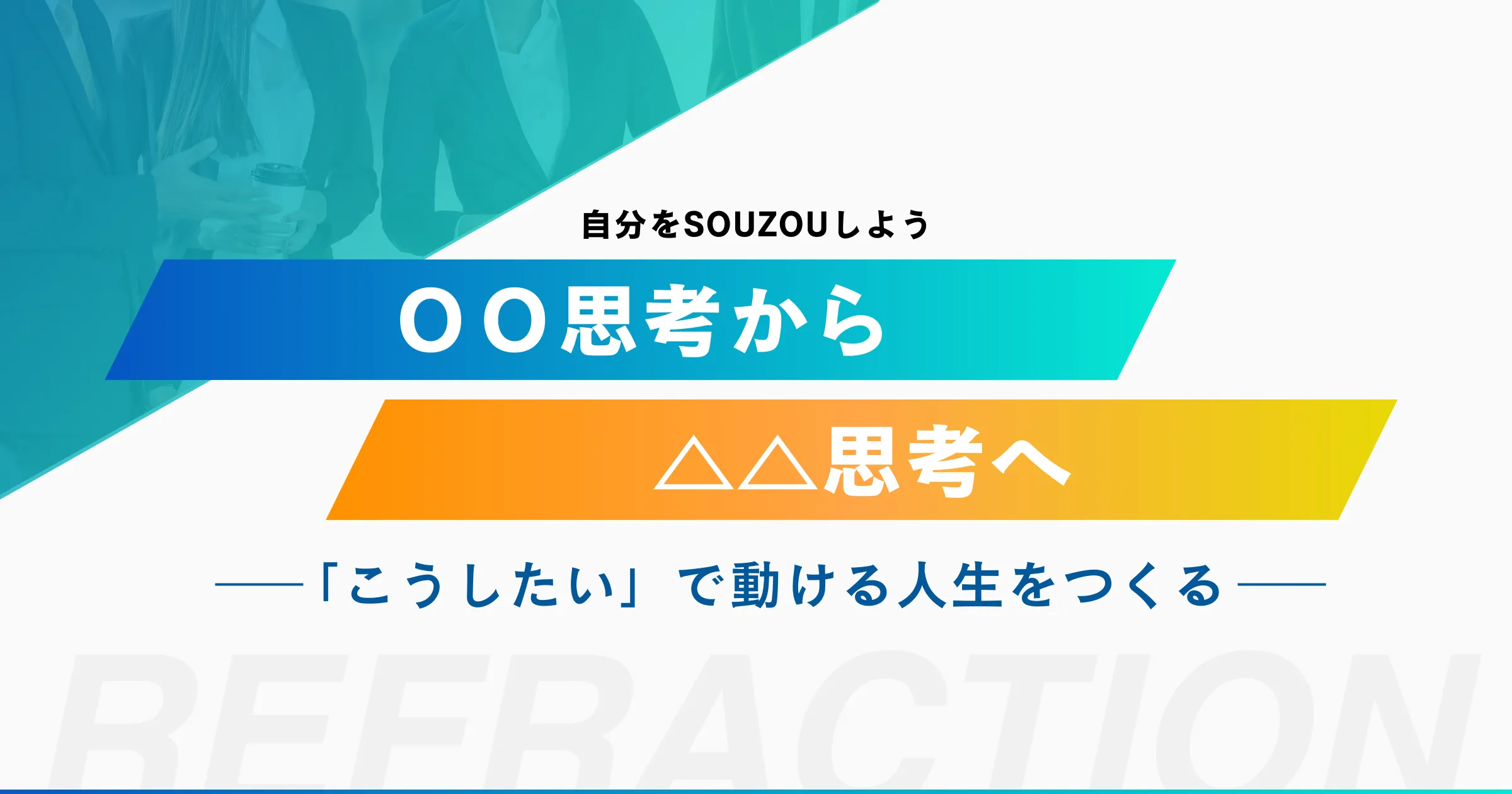
はじめに
日々の生活や仕事、家族・周囲からの期待に応えようとするうちに、「本当はどうしたいのか分からない」「なりゆきでここまで来てしまった」という思いにかられたことはありませんか?
本記事では、「こうするしかない」という受け身の思考を、「こうしたい」という主体的な思考に切り替えることで、より納得感のある目標を設定し、自分らしい人生を歩んでいくためのヒントをお伝えします。
1.「〜しなければ」という”Have to思考”が生み出す停滞感
■ そもそも「Have to思考」とは?
「Have to思考」とは、「○○しなければならない」「やるしかない」といった“義務感”や“強制感”に基づいた思考のことです。
本心では望んでいないのに、「周囲の目を気にして」「常識だから」「失敗したくないから」といった理由で行動を選択し続けてしまう――そんな状態が「Have to思考」の典型です。
■ よくある思考パターンの例
- 「本当は転職したいけど、家族がいるから我慢するしかない」
- 「やりたいことがあっても、収入にならないなら意味がない」
- 「今さら挑戦して失敗するのは恥ずかしいから、現状維持でいい」
- 「自分の気持ちより、周りに迷惑をかけないことが大事だ」
これらは一見、責任感があるように見えますが、すべて“外側の正しさ”や“他人の価値基準”に合わせているため、自己決定の感覚が失われていきます。
主体性のある人生を歩んでいく上で、この「Have to思考」は弊害になることがほとんどです。
■ なぜ「Have to思考」に陥ってしまうのか?
多くの人が「Have to思考」に陥る背景には、以下のような要因があります。
- 幼少期からの刷り込み:「ちゃんとしなさい」「迷惑をかけるな」といった教育や環境によって、他人軸の判断基準が身についている
- 社会構造や同調圧力:「普通はこうするもの」「常識的に考えて」といった空気が、自分の感情を抑え込む
- 過去の失敗・挫折経験:「また同じようなことになったら…」という恐れが、“挑戦より安全”という選択を優先させてしまう
つまり、「Have to思考」は一人ひとりの内面から生まれているというより、社会的な背景やこれまでの経験によって形づくられてきた“防衛的な思考パターン”とも言えるのです。
■ 「Have to思考」がもたらす3つの弊害
- 納得感の欠如
「自分で選んだ」という感覚が薄いため、どんなにうまくいっても心が満たされず、「なんか違う」と感じることが増えます。逆にうまくいかなかったときは、「やっぱり自分はダメだ」と自己否定につながりやすくなります。 - 行動の停滞とエネルギー消耗
やりたくないことを“やらなければ”と頑張り続けると、精神的な疲労が蓄積され、モチベーションも下がります。その結果、行動のスピードが鈍り、現状維持を選ぶようになってしまいます。 - 視野が狭まり、柔軟な発想ができなくなる
「○○でなければならない」という前提で考えると、他の可能性を検討する余白がなくなります。発想力や創造性が奪われ、新しい選択肢が見えにくくなります。
このように、「Have to思考」は一見“真面目”や“安定志向”というポジティブな姿に見えることもありますが、実際には自分の人生を狭く・苦しくしてしまう大きな要因にもなり得ます。
だからこそ、この思考から一歩外に出て、自分の「Want(こうしたい)」に耳を傾けることが、納得感のある人生の第一歩なのです。
2.「〜したい!」という”Want to思考”がもたらすもの
■ 「Want to思考」とは、“Be”から始まる思考
多くの人が「こうしたい」と考えるときに、無意識のうちに「どうやればできるか(How)」や「何を得たいか(Have)」という視点に引っ張られます。
けれど、それでは現実の制約や常識から抜け出せず、結局「今できそうなこと」しか見えません。
本当の意味での「Want to思考」は、
How(方法)でもHave(モノ)でもなく、“Be(どうありたいか)”を出発点にすること。
- どんな自分でありたいのか?
- どんな感情を味わっていたいのか?
- どんな雰囲気の中で生きていたいのか?
この“存在の在り方”から出発することで、初めて現実を超えた自分本来の望みにアクセスすることができるのです。
■ Want toを見つけるための「本質的な問い」
Want toを見つけるためには、まず現実の制約を外す力強い問いかけが必要です。以下は、内側からの答えを引き出すための代表的な質問例です。
【1】「あと4週間で人生が終わるとしたら、どう過ごしますか?」
- 最初の1週目は何をしたい?
- 誰と、どこで、何を話したい?
- 最後の10日はどう過ごしたい?
👉 時間が限られているとき、人は「本当に大切なもの」しか選べなくなります。これは心の奥底にある“優先順位”を見つける質問です。
【2】「明日10億円を手にしたとしたら、どんな暮らしをしますか?」
- その日から、何を変えますか?
- どんな一日を送り、誰と会い、どんな感情で過ごしていますか?
👉 お金の制約がなくなったとき、あなたの“本音”が現れます。お金が欲しいのではなく、自由・安心・創造性といった状態を求めていることに気づけるかもしれません。
【3】「10年後、すべてが思い通りになっていたら?」
以下の問いを想像しながら、できるだけ具体的に描写してみてください:
- どんな場所に住んでいる?
- どんな格好をしている?(スーツ?カジュアル?)
- 周囲にはどんな人がいて、どんな表情で過ごしている?
- あなた自身は、どんな表情をしている?
- 思い通りの10年後の“典型的な1日”を、時間単位で書き出してみましょう
👉 この質問は、「あなたの人生の本質的な理想形」を引き出す強力な視点です。「こうなりたい」ではなく「こう“在る”ことが自然で心地いい」という“Be”の状態に触れやすくなります。
■ Want to思考を阻む「やってはいけないNGパターン」
Want to思考に切り替えるとき、次のようなゴール設定には注意が必要です:
- 「年収1000万円を稼ぎたい」
- 「高級車に乗りたい」
- 「タワーマンションに住みたい」
これらは一見「Want to」に見えますが、実は Have(所有)にフォーカスした願望であり、目的ではなく“手段”にすぎません。
✔️ 本当に大切なのは、その先に何を感じたいのか?どんな自分で在りたいのか?です。
✔️「なぜ、それが欲しいと思ったのか?」と深掘りすることで、「Be」にたどり着くヒントが得られます。
■ Want to思考がもたらす変化
- 自分の軸が明確になる
他人の価値観や社会の正解ではなく、「私はこう在りたい」という軸を持つことで、選択に迷いがなくなります。 - 行動の意味が変わる
目の前の行動が「やらなきゃ」ではなく「やりたいからやってる」状態になることで、自然とエネルギーが湧き、継続も苦にならなくなります。 - 結果よりもプロセスを楽しめる
Beが明確であるほど、今の過程そのものに意味を感じられ、「いつか満たされる」ではなく「今すでに満たされている」状態を生きられるようになります。
■ Want to思考の本質とは?
Want to思考のゴールは、“成功”ではなく“納得”です。
それは、「他人にどう思われるか」ではなく、「自分がどう在りたいか」を問い続けること。
Be(どう在るか) → Do(何をするか) → Have(何を持つか)
この順序を意識できるようになると、あなたの人生の軸は静かに、しかし力強く変わっていきます。
3.「Have to思考」から「Want to思考」へ切り替える3ステップ
実際に「Have to」から「Want to」へ思考を切り替えるためには、どうすればいいのでしょうか。ポイントは、「一度、現実の制約を取り払って考えてみる」ことです。
ステップ1.現実の制約を一旦取り払う
お金や評価、家庭やキャリアなど、私たちが日々抱えている制約は多岐にわたります。しかし、その制約があるために「本当はこうしたいのに…」という想いを押し殺していないでしょうか。
まずはそれらを脇に置いて、「もしすべてが自由だったとしたら、あなたはどうしたいですか?」という問いを自分に投げかけてみてください。
ステップ2.「どうなったらワクワクするか?」を基準に考える
制約を取り払った空想の中で、「自分が心からワクワクする状態」をイメージします。
たとえば、「世界中を旅しながら仕事をしたい」「自分の作品を発表する場がほしい」「時間に追われず、好きなことで生計を立てたい」など、心が弾む妄想を遠慮せずに描きましょう。
そうしたイメージこそが、あなたの心の奥にあるWantを見つけるきっかけになります。
ステップ3.Wantをもとにゴールを設定し、現実とすり合わせる
見つけ出したWantが、自分にとって本当に大切だと感じるなら、そこから逆算してゴールを設定してみましょう。ここでようやく、現実的な要素を加味していきます。
- どんなスキルや人脈が必要か
- 具体的にはどのくらいの資金・期間が必要か
- 家庭や仕事との両立はどう可能か
一度自由に想像した後で、今の生活とすり合わせてみると、「現実的にはすべてを叶えきれないけれど、この一部分ならできるかもしれない」と気づくことがあります。小さくても、実際に始めてみることで「Want to思考」が現実に少しずつ根付いていきます。
4.「Want to思考」がもたらす人生の変化
■ 続けられるから、自信が生まれる
「やらされている」と感じるタスクは途中で挫折しがちですが、「やってみたい」と思うことは続けやすいもの。小さな成功体験や達成感が積み重なることで、自分への肯定感が増し、新たなチャレンジへの後押しにもなります。
■ 人生の方向性がクリアになり、未来への展望が開ける
自分の内面に目を向け、「本当はこうありたい」という道筋が見えてくると、優先順位をつけやすくなります。すると日常の選択にも迷いが減り、「今これをやるべきだ」「ここはあえて断ろう」といった判断がしやすくなり、未来への展望がよりクリアになっていきます。
5.読者へのメッセージ
- 「これでいいのか?」と疑問を抱くあなたへ
今まで周囲に合わせて生きてきたと感じるなら、まずは「あらゆる制約を取り払って、自分が本当はどうしたいのか」を考えてみてください。 - モヤモヤして一歩が踏み出せないあなたへ
もしかしたら、「考える余裕がない」と思い込んでいるだけかもしれません。少しだけ日常を離れて、思考の枠を外す時間を作ってみることをおすすめします。 - 失敗を経験しつつも、もう一度自分と向き合いたいあなたへ
過去の失敗や挫折は、あなたを定義する全てではありません。一度うまくいかなかっただけで、あなたの「こうしたい」という気持ちまで否定する必要はないのです。再び向き合うことで、新しい可能性が見えてくるはずです。
おわりに
「Have to思考」から「Want to思考」へシフトするのは、決して簡単なことではありません。
社会的なプレッシャーや身近な環境はすぐには変わらないかもしれません。
それでも、思考の出発点を「こうしたい」に置くことで、自分の人生に対する納得感と主体性は大きく変わります。
現実を見つめながらも、あなたの心の奥底にある“本当の望み”を大切にしましょう。
そこに気づき、行動を起こしたとき、人生の新たな方向性がきっと見えてくるはずです。